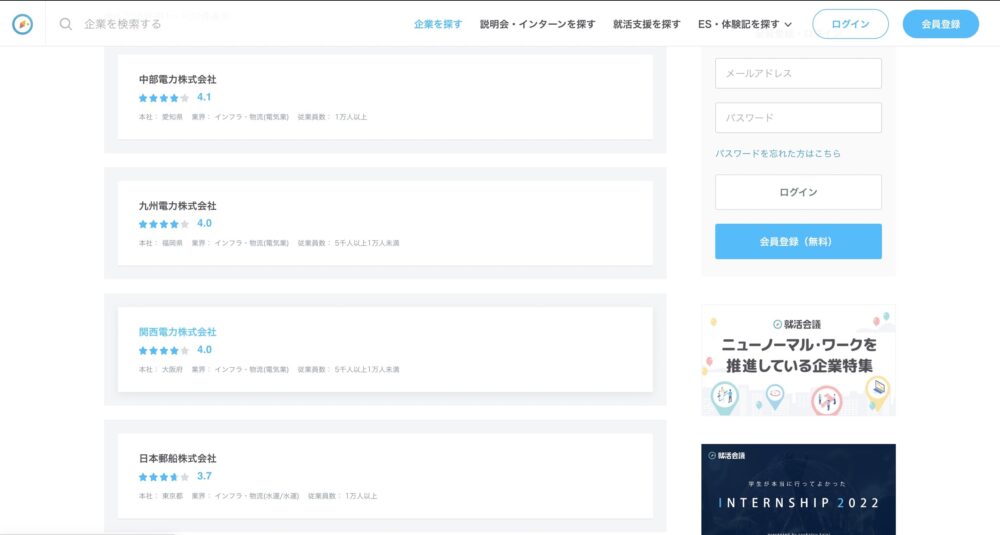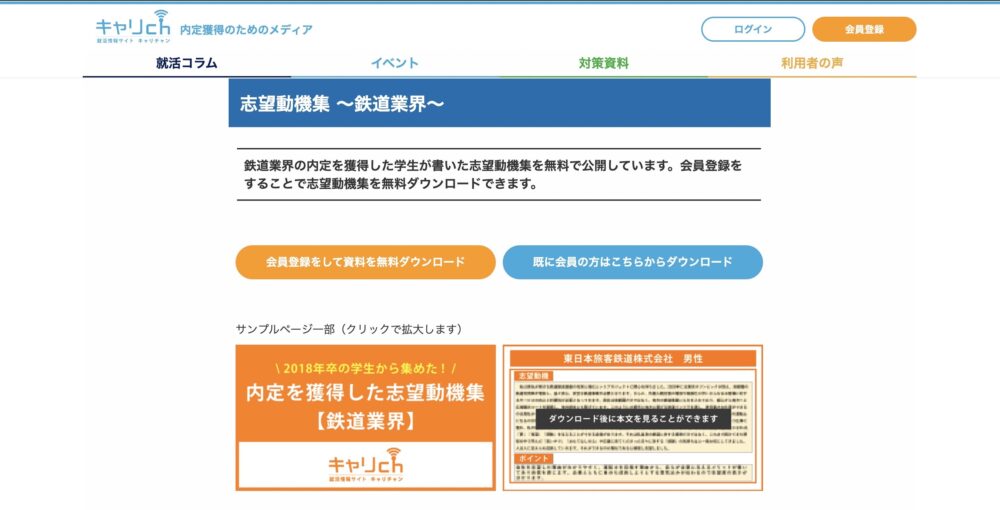お疲れ様です!
インフラ業界総合職で現在入社5年目のゆうゆうと申します!
「SDGsに対する企業の取り組みが知りたい」
「MaaSって聞くけど、何?」
と思っていませんか?

今回の記事を読んでいただければ、それらの心配を解決することができます。
今回の記事で説明するのは、今後の交通インフラ業界を大きく変える可能性を持つ「MaaS」というサービスについてです。
このMaaSの発展はSDGs11 「住み続けられるまちづくりを」の達成に貢献することができるんです。
今回、説明するのは以下の内容です。
- SDGsとは
- MaaSとは
- 各企業の取り組み
今回の記事では以下のような読者を対象としています!
- インフラ業界志望者 ← メイン
- インフラ業界への転職希望者 ← メイン
- MaaS・SDGsについて知りたい人
- インフラ業界への投資を考えてる人
それでは説明していきます。
SDGsとは

全世界の目標SDGs
SDGsは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」を略した言葉です。
SDGsと書いて、「エス・ディー・ジー・ズ」と読みます!
SDGsはざっくり言うと、世界中の人々が一つになって解決すべき地球規模の課題なんです。
「SDGs11.産業と技術革新の基盤をつくろう」について

SDGsは17の目標が設定されています。
今回説明するのは、「SDGs11.産業と技術革新の基盤をつくろう」についてです。
都市部への集中が進む現代において、都市部の環境悪化や災害被害の分散ができてないことへの対策が重要になってきてます。
それらの現状打破を目指すために目標11は設定されました。
また、SDGsには17の目標に対して、具体的な169の「ターゲット」、つまり小さい目標が設定されており、17の目標に振り分けられています。
「11.産業と技術革新の基盤をつくろう」のターゲットは以下のような内容が含まれてます。
- 11.1 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。
- 11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者、および高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。
- 11.7 2030年までに、女性・子ども、高齢者および障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。
MaaSとは

MaaSの概要
MaaS(マース)はMobility as a Service(モビリティ・アズ・ア・サービス)を略した言葉です。
MaaSはまだ日本では広まり始めたばかりの概念ですが、今後交通インフラ業界に大きなイノベーションを起こすと期待されています。
MaaSとは簡単にいうと、スマホアプリ一つで複数の交通サービスのルート検索、予約、決済までの全てができるサービスです。
これまでの社会では、短距離の移動に関してはマイカーを利用し、
長距離の移動では利用者自身が飛行機、新幹線、バス、タクシーなどを利用者が各社のサイトで調べて、
どの組み合わせのルートが最も早いか、最も安いかなどを考えながら決定していました。

しかし、マイカーは所有時間の2%しか利用されないため、所有することがが本当に良いのかという課題がありますよね。
また長距離移動に関しては、時間がかかり、膨大な量の組み合わせがあるため、どれが最適なルートかがわからないという課題がありました。
しかし、MaaS社会が実現するとDoor to Door(ドア・トュー・ドア)で利用者に最適なルートを1つのアプリが提案し、決済までできるようになります。
海外で行われているMaaSのサブスクリプションサービス、つまり5km圏内の電車、タクシーなどの乗り放題サービスは1ヶ月3万円〜5万円で利用ができます。
マイカーの維持費は毎月3万円で、そこに購入費が乗ってきます。
そう考えると、マイカー所有と値段は変わりませんし、自分で運転しなくて良い分、得してますよね。
つまり、マイカーに代わる選択肢になるんです。

そして、MaaSには利用者の負担を減らす以外に、社会問題を解決するポテンシャルも秘めています。
それは交通手段の最適化による、都市の渋滞・環境問題、過疎化、高齢化が進む地域の移動手段創出、など多くの問題を解決できることです。
まとめると、MaaSはマイカーという魅力的な選択肢の対抗策であり、多くの社会問題を解決する可能性を持ち、持続可能な社会を構築する概念です。
そのため、MaaS社会の実現はSDGs11 「住み続けられるまちづくりを」の達成につながるんです。
MaaS社会を実現させるためには

MaaS社会を実現させるためには、「強いリーダーシップが必要」です。
交通サービスに関わる企業は、航空会社、鉄道会社、タクシー会社、バス会社、自転車シェアリング会社、カーシェアリング会社など多岐に渡ります。
これらの企業が協力しなければ、MaaS社会は実現しません。
しかし、企業は営利団体である以上、自社の利益を優先して動きます。
そのため、これらの企業をまとめるのは非常に難しいです。

それこそ、これらの企業の一つがリーダーになろうとすると、他の企業から
「あの企業はリーダーの振りして、利益を独り占めしようとするんじゃないのか?」と、
疑われて、足の引っ張り合いが始まります。
その状況を回避するためにも強いリーダーシップが必要なんです!
MaaSが上手く進んでいるスイス、フィンランドなどの国では、政府が中心になってMaaSを進めています。
日本は各企業が独自にMaaSを進めている状況なので、まだまだ認知されるのに時間はかかりそうですね。
MaaS社会が実現した時のメリット

MaaS社会の実現は、マイカー依存型社会の脱却に繋がります。
マイカー依存型社会からの脱却は非常に多くのメリットを僕たちの社会に提供してくれます。
簡単な例を挙げますね。
- 駐車場を探す手間がなくなる
- 渋滞に捕まらなくなる
- 駐車場が減る分、街のスペースが増える
- 排気ガスが減る
- 駅や空港などの公共交通インフラ側に投資が増え、住みやすいまちづくりが進む
- 交通事故の削減
- マイカーを所持できない高齢者等の”足”になる
- 自動車会社ではなく、地域にお金が落ちるようになる
特に、今回説明したいのは「マイカーを所持できない高齢者等の”足”になる」という部分です。
政府の調査で、2050年に徒歩圏内に生鮮食品が存在しない高齢単独世帯の数が114万世帯、2005年と比較すると2.5倍になるだろうというデータが出ています。
また、車の使えない高齢者が2015年時点で825万人以上いるというデータも出ています。
このような、買い物難民がいる社会は決して「持続可能な社会」ではありません。
MaaS社会が発展し、マイカーに代わる選択肢にまで成長すればこれらの買い物難民問題を解決することができるんです。
そのため、少子高齢化が進む日本にとってMaaSは、絶対に注目しなければいけない話題なんです。
各企業の取り組み
鉄道業界

JR東日本
JR東日本は鉄道会社の中で、特にMaaSに力を入れている企業の一つです。
交通ICカードサービス「Suica」を中心としたプラットフォームを構築しており、
顧客の移動、検索、決済データをsuicaを通して収集し続けることで、
持続可能なサービスを提供できる仕組みとなっています。
さらに、JR東日本のMaaS推進グループは3つのプロジェクトを現在進めています。
- Ringo pass(リンゴパス)
- AI運行バスの利用
- 自動運転バス
Ringo pass(リンゴパス)
RIngo passはSuica IDを利用することで、地図上のタクシーや自転車シェアを使うことができるアプリです。
AI運行バスの利用
横浜で行われたAI運行バスの実験では、駅に用意された端末にSuica IDを登録することで、AI運行バスが利用できるという内容でした。
自動運転バス
JR東日本の竹駒駅周辺でバス専用道路での自動運転バスの運行を予定してます。
JR東日本に関しては、「JRについての記事」でも詳しく解説しています。
小田急電鉄

小田急電鉄はMaaSを利用した沿線価値の向上を目指しています。
小田急電鉄がターゲットにしているのは主要駅から車で20分以上離れた距離にある住宅街です。
これらの住宅街は交通サービスが不便なことから、高齢化が進むにつれて、土地価格も減少していきます。
しかし、この主要駅と住宅街を高頻度で往復してくれる自動運転バスがあれば、住宅街は栄えたまま、
鉄道客も増えるのではないか?と仮説を置き実験を進めています。
2018年に江ノ島で実験が行われており、今後も注目される分野です。
関東私鉄に関しては「関東私鉄についての記事」でも詳しく解説しています。
航空業界

ANA
ANAは「ANAそらたび検索」というサービスを利用して、コロナ時代での移動需要の創出を目指しています。
「ANAそらたび検索」 は、飛行機での移動を検討しているお客様に対して、
お客様のスケジュールや条件にあわせて、ANAの飛行機と地上の交通インフラを組み合わせた経路を提案するサービスです。
具体的にいうと、ANAの企業サイトと連動した飛行機の空席状況や料金をいつでも確認でき、
乗り換え時間に無駄のない航空券の予約が可能になるサービスです。
ちなみに、MaaS社会における航空業界の課題は空港までのアクセス手段が多様な点です。
そのため、飛行機が遅延、欠航した場合などのイレギュラー時にすぐに新しい二時交通を提案できることが求められます。
その課題に対しする解決策として「ANAそらたび検索」は、期待されているんです。
ANAについては「ANAとJALの比較についての記事」でも詳しく解説しています。
電力業界

関西電力
関西電力は持続可能な社会実現のために、充電インフラの整備を通じたEV拡大を目指しています。
そして、それらのEVを軸にエネルギーとモビリティの融合を進めています。
具体的な取り組みとしては、時速5キロメートルの低速走行自動運転車両「iino(イーノ)」の開発があります。
iinoは関西電力の若手中心に推進しているプロジェクトで、
大型ショッピングモールや大都市での走行者に対して、立った状態で気軽に乗れる「type-S」と、
観光地やリゾート地で寝ながら乗れるベッドタイプの「type-R」があります。
関西電力に関しては、「電力業界についての記事」でも詳しく解説しています。
通信業界

通信業界とMaaSは非常に相性がいいです。
それは通信業界に起きたイノベーションである「5G」とMaaSの親和性が高いからです。
5Gの特徴は「速くて」「たくさん」「遅れずに」通信ができることです。
そして、この特徴は自動運転に大きく貢献することが期待されています。
なぜなら、自動運転には遠隔監視や遠隔操作が必要であり、それらの達成には5Gの技術レベルでないと対応できないからです。
自動運転はMaaS社会においてはなくてはならない技術です。
そのため、MaaS社会発展には通信業界の発展、つまり5Gの発展が必要不可欠なんです。
5Gに関しては、「5Gについての記事」でも詳しく解説しています。
NTTドコモ

NTTドコモは2015年という非常に早い時期からMaaSに取り組んできた企業です。
NTTドコモがMaaSに対して手掛けてきたのは以下の事業です。
- 自転車シェアリング事業
- カーシェアリング事業
- AI運行バス事業
- タクシー配車事業
そして、これらのサービスに対して、dポイントでスマホ決済ができ、顧客の囲い込みができているのがドコモのすごい点です。
自転車シェアリング事業とカーシェアリング事業を簡単に紹介します。
自転車シェアリング事業
2015年2月にドコモ・バイクシェアを設立しました。
ドコモの自転車シェアリングとは、乗りたい時に借りて、着いた場所で返すことのできる自転車共有サービスです。
ドコモの駐輪場にある自転車にICカードをタッチすることで誰でも借りることが可能です。
どこでも返せる点が非常に魅力的ですよね!
カーシェアリング事業
2017年10月にdカーシェアを設立しました。
dカーシェアでは、レンタカー、カーシェアをサービスとして行っています。
レンタカーのメリットとして
- 豊富な車種から選択できる
- 長期間の車の利用に便利
カーシェアのメリットとして
- 24時間いつでも使える
- 15分から利用可能
- ガソリン代や保険料が無料
ことが挙げられます。
NTTドコモについては「NTTについての記事」でも詳しく解説しています。
ソフトバンク

ソフトバンクはトヨタ自動車と組むことで、MaaSのキープレーヤーになった通信会社です。
ソフトバンクは2018年9月にトヨタ自動車とMaaSを推進するための合弁会社「モネ・テクノロジー」を設立しました。
モネ・テクノロジーは将来の自動運転社会を見据えて、自動運転車両を活用した移動型コンビニや病院、
オフィスなど、新たなモビリティサービスを創出することを目指す企業となってます。
この超大企業が手を組んでできたモネ・テクノロジーの動きからは目が離させませんね!
まとめ

今回の記事では、SDGs11(まちづくり)への交通インフラ企業の取り組み『MaaS』について解説してきました。
解説したのは以下の内容です。
- SDGsとは
- MaaSとは
- 各企業の取り組み
MaaS社会の実現はマイカー脱却社会の実現に繋がります。
マイカー脱却社会が実現すれば、排気ガスが減少し、高齢者などが気楽に移動できる世界が実現します。
その結果、住みやすいまちづくり、持続可能な社会の実現となり、SDGsの達成に繋がるんです。
だからこそ、多くの企業がMaaSに投資を行っています。
そのため、インフラ業界を目指す就活生には今回の記事をきっかけに「MaaSとは何か?」ということを理解していただきたいです。
また、SDGsに関しては「SDGsについての記事」「SDGs5 ジェンダー平等についての記事」「SDGs7・13対策、カーボンニュートラルについての記事」「SDGs達成のためDXの取り組み記事」でも詳しく解説しています。
「就活会議」と「キャリch」は無料で内定した先輩のエントリーシートが見放題のサービスです。
両方とも非常に有名かつ実績のあるサービスなので、少なくともどちらか一つは登録することをオススメします!
就活口コミサービス「就活会議」このブログではインフラ業界志望者のための記事を多数準備しています。
インフラ業界については「インフラ業界についての記事」「インフラ業界優良企業ランキング記事」でも詳しく解説しています。
 インフラびより
インフラびより